2025年11月6日(木)TOC学会新潟に参加しました。
このTOC学会は日本全国で行われています。大阪開催の主催は私たちせんばTOCの原と田中で運営をしています。
この度、私たちの師匠である清水先生のおひざ元、新潟開催のTOC学会となりますが主催者に名前を連ねていただいています。複数名のシニアインストラクターで共同で主催という形をとらせていただいております。やはり新潟は気合入ります!
まずはTOCとは?のご説明をします。
「一生懸命頑張っているのに、なぜか会社全体で見ると成果が出ない」「改善の取り組みが、いつも一部の部署で止まってしまう」――。もしあなたがこのような悩みを抱えているなら、TOC(Theory of Constraints:制約の理論)という考え方が、その突破口を開いてくれるかもしれません。
TOCは、システム全体の成果を制限している、最も弱いリンク(制約、ボトルネック)を見つけ出し、そこに知恵と資源を集中させることで、組織全体を最適化するための、シンプルかつ非常に強力な経営哲学です。
TOCの魅力は、業種や規模を問わず適用できる普遍性にあります。ここでは、TOCの考え方を活用し、経営の「流れ」を劇的に改善した具体的な事例を、会社名を伏せてご紹介します。

1. 複雑な業務に「流れ」を生み出し、現場の負担を軽減する
多くの現場では、複雑な業務が絡み合い、ベテランの社員に負担が集中しがちです。TOCは、まず業務プロセスを明確にし、ボトルネックを特定することで、無理のない業務フローを再構築します。
事例:医療サービス関連A社様(薬剤師の生産性向上)
外来と、処理に時間のかかる在宅訪問という、異なる性質の処方箋が混在する現場で、業務の両立が大きな課題となっていました。
• TOC活用: 複雑な外来フローと在宅フローを詳細に可視化(視える化)し、
時間がかかる工程(ボトルネック)を把握しました。
特に時間がかかる訪問同行業務に対して、あらかじめバッファ(緩衝時間)を設定し、
納期に関するルールを明確化しました。
• 具体的な工夫: 複数の作業工程を組み替えることで、「手戻り」を徹底的になくす仕組みを導入しました。
また、作業に使う備品にアラーム情報を付けるなど、進行具合を見える化する工夫を取り入れました。
• 成果: 人員を増強することなく新規の依頼に対応できる体制が整い、結果として薬剤師の生産性が向上し、
年間で粗利が大幅にアップしました。
さらに、TOCを共通言語として教育に組み込むことで、社内全体への普及も進みました。
2. 小ロット生産でも対応力を高め、安定した経営基盤を築く
製造業やアパレルなど、多品種少量生産を行う企業にとって、在庫管理やリードタイムの短縮は永遠の課題です。
事例:製造業B社様(企画・生産の効率化)
多品種小ロット生産を基本とするB社様は、市場の変化に対応するため、生産管理の考え方を抜本的に見直しました。
• TOC活用: 「業界の常識が必ずしも真理ではない」という視点から、新商品よりも定番商品の欠品や機会損失防止に注力する方針を確立しました。在庫管理の最小単位(SKU)を抑制しました。
• 具体的な工夫: 従来、月1回一人で行っていた在庫確認作業を、スタッフ複数名による週次の確認体制へ変更し、アラートを共有シートで管理することで、抜け漏れを防ぎました。また、複雑だった見積書作成プロセスを簡略化し、仕様を入力するだけで工賃が確定するシートを共有することで、発注にかかるリードタイムを他社と比較して大幅に短縮しました。
• 成果: 在庫確認や発注にかかる時間が半減し、スタッフのストレスが軽減しました。検証の結果、小ロット生産が基本方針として最も適していることをデータで裏付けることができました。
3. クリエイティブな業務における「選択と集中」とプロジェクト管理
TOCは、発想力が重要となる設計業務や、多くのタスクが並行するプロジェクト管理においても、その力を発揮します。
事例:機械設計・制作C社様(設計・現場業務の改善)
お客様の要望に応じた機械の設計・制作を行うC社様では、特に発想力を要する「機構を考える工程」がボトルネックとなっていました。
• TOC活用: ボトルネックを生かすために「選択と集中」を実施しました。設計ソフトに部品データを事前に登録するなど、非クリエイティブな作業工程を削減し、設計者はボトルネック工程に集中できるようにしました。
• 具体的な工夫: 複雑な組み立て業務には、CCPM(クリティカル・チェーン・プロジェクト・マネジメント)の考え方を取り入れ、バッファを設け、3色のアラーム情報で進捗を管理する仕組みを導入しました。これにより、作業の「見える化」と「気づき」の仕組みが実現しました。
• 成果: 業務フローの可視化によりリードタイムが短縮され、全体最適が実現しました。進捗の認識のズレを防ぐことで、納期直前まで作業をしない「学生症候群」も解消され、ボトルネックの負担軽減につながりました。制御作業時間も大幅に減少しました。
事例:金融・教育サービスD社様(教育と成果の両立)
D社様では、社員教育にベテランのFP(ファイナンシャルプランナー)の時間が取られ、結果的に会社の利益を示すMQ(スループット)が下がってしまうという、「教育とMQのトレードオフ」の課題に直面していました。
• TOC活用: 教育とMQは両立できるという前提に立ち、ボトルネックであるベテランFPの時間を有効に使う仕組みを構築しました。
• 具体的な工夫: 新入社員を単なる研修生ではなく、FPの補助役として業務に組み込み、ベテランの負担を軽減しました。新入社員にも権限とMQを生む役割を渡すことで、双方にとって効果的な教育サイクルが生まれました。
• 成果: 組織は効率化し、少数精鋭になってもMQが上がり続け、連続で単月黒字を達成しました。特に、教育や人材の領域においてもTOCは有効であり、「違和感を放置しないことが工程を流す第一歩となった」という重要な教訓を得られました。
TOCは、組織に「質の良いコミュニケーション」と「共通言語」をもたらします
TOCを導入することは、単なるテクニックの導入ではなく、組織が抱える「心のモヤモヤ」 や、共通認識のズレを解消するプロセスです。
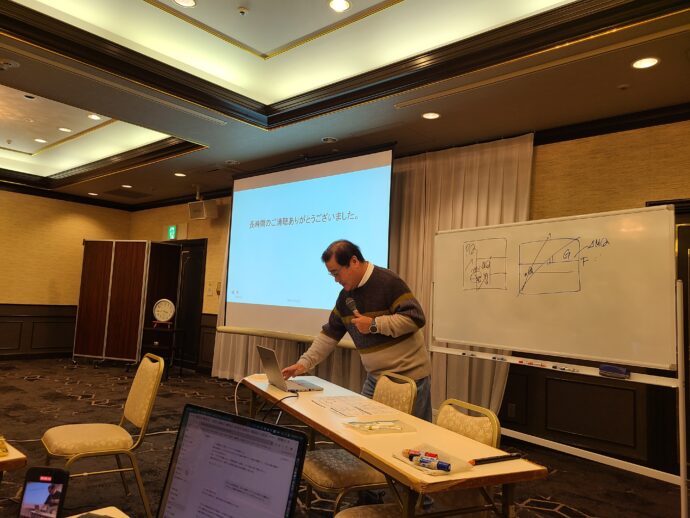
多くの事例で共通するのは、「頑張っているのに報われない」と感じる状態から脱却し、会社のゴールと、チーム、個人の目標が明確につながっている状態を築くことです。
TOCは、ボトルネック特定やバッファ管理に加え、MQ会計(スループットを重視した会計手法)を組み合わせることで、誰もが同じ指標を見て、建設的な会話(質の良いコミュニケーション)ができる共通言語を提供します。
そして、TOCの実践は、究極的には「結局やるかやらないかである」というシンプルさに集約されます。共通の理解に基づき、組織が一丸となって継続的な改善サイクルを回すための羅針盤、それがTOC(制約の理論)なのです。
TOCによる変革は、会社という名のオーケストラを指揮することに似ています。才能ある演奏者(各部署や社員)が、それぞれバラバラに最高の努力をしても、音楽(経営成果)は最高の状態にはなりません。TOCは、全体の流れを把握し、今、最も音量が不足している楽器(ボトルネック)を見つけ、そこに指示(資源)を集中させることで、調和が取れた最高の演奏(全体最適)を実現するのです。
